
10:00~19:00 日曜・祝日を除く
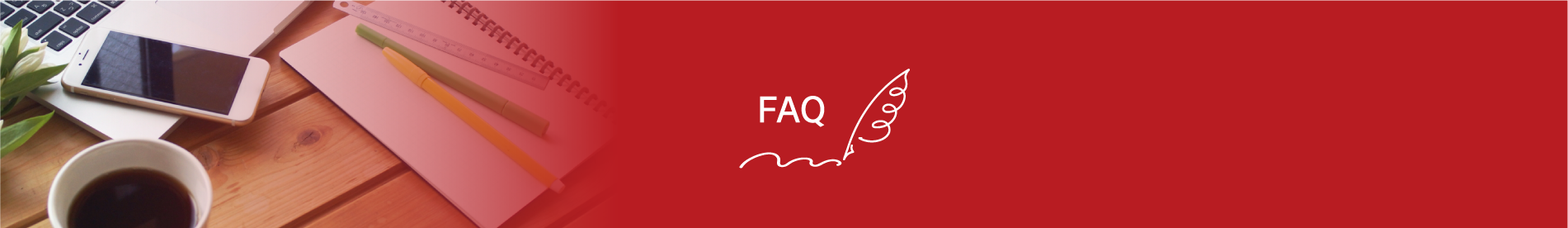
多くの日本語教師養成講座は420時間の通学の受講時間に合わせてプログラムが組まれています。その上ほとんどが日本語教育検定試験合格(合格率20%前後)を目的としたもので、授業料も60万円前後で期間も1年間ぐらいかかります。
またこれらは直接法を主体にした教授法です。本講座は日本語教育検定試験合格を主目的にしたものではありません。
本講座は「英語話者の生徒に日本語を教えたい。」という人のために、媒介語の英語を用いて、発音のためにローマ字を使いながら初級から中級にかけての日本語の教え方を学ぶのが目的であり、「動詞を制するものはその言語を制する」と言われているように動詞を中心に耳と口を使って徹底的に音から日本語を教えていきます。
教室で生徒を前にして日本語を教える最低限の知識とテクニックを40時間程度で習得します。ですから結果的に授業料も安くなります。
国内と海外では違ってきますので別々に考えてみましょう。
【国内】
①日本語学校で教える。または各種専門学校の日本語科で教える。
②語学学校で日本語科を作りそこで教える。
③自分で生徒を集め教室を作りそこで教える。
④副業として教える。
①については検定試験合格者が優先されます。あとは運とコネ次第です。
②~④は基本的に自分自身で生徒を探さなければなりません。
その方法を考えて見ましょう。
①その地域の新聞等に広告を出す。
②チラシを作り外国人が集まりそうなところを調べ、そこに置かせてもらう。
③外資系の会社や外国人を雇っている会社を調べる。
【海外】
①現地の日本語学校で教える。
②英語学校等で日本語の教室を作りそこで教える。
③自分で生徒を集め個人教室を作る。
①については自己アピールと直接法よりもその国の言語を使った間接法の習得が最低条件です。もちろん運とコネも関係してきます。
②~③は基本的に自分自身で生徒を探さなければなりません。
その方法を考えて見ましょう。
①その地域の新聞等に広告を出す。
②チラシを作りポスティングする。
③日系企業をあたってみる。
④日本人の観光客が多く利用するホテル、レストラン、お土産や、免税店等をあたってみる。
1986年にニュージーランドのオークランドで英語学校の教室を借りて日本語を教えたのが私の日本語教師のスタートでした。
最初の生徒は一人でプライベートレッスンでした。いずれにしても大事なのは一人の生徒を大事にすること。
良いレッスンをすれば生徒が生徒を紹介してくれます。自分を信じて日本語教師の道を歩き出してください。
一般的に日本語教師になるために必ず取得しなければならない資格はありません。
現在のところ日本語教師の公的な資格制度は確立されていないため、日本で唯一公的に認
められている日本語教育能力検定試験の合格者が資格者に準ずる扱いを受けているのが実状です。
主に国内の日本語学校が日本語教師を採用する場合、日本語教育能力検定試験合格者が優先される場合が多いことは確かです。
4年制大学で日本語教員養成課程の主専攻か副専攻を修了し卒業した人、民間の日本語教育機関の日本語養成講座を420時間(副専攻の26単位分)受講した人も検定合格者と同等とみなすと言われていますが、実際はそれだけでは実力の証明にはならず、大学生も民間の日本語教育機関の受講生も試験を受けて合格を目指しているのが現状のようです。
この日本語教育能力検定試験に備え、貴重な時間とお金を費やして専門的な勉強をしているのにもかかわらず、実際は受験者の合格率は20%前後です。
この検定試験は日本語教育の知識能力を問うものですが、出題範囲が多岐にわたり受験者には現場の日本語教育に必要な知識以上のものが要求されるのも事実です。
また実際の教育現場では知識だけではなく練習のさせ方などの技術面も求められますが、検定試験は筆記試験のみで練習のさせ方などの実施試験はありません。
60万円前後の授業料を払い、1年ほどかけて420時間の養成講座を受けて検定試験の合格を目指して努力しても合格率はたったの20%前後でかなりの難関です。
しかも合格しても日本語学校に必ずしも就職できるとは限りません。
ですが反対に試験に落ちても就職できないともいえません。それは雇う側と雇われる側の関係になってくるからです。
いずれにしても良い日本語教師になるためには、最低限の日本語の知識(主に文法)と実践的なテクニックが必要になります。
本講座は10週間でローマ字を使い初級から中級にかけて日本語学習者に教えられる日本語教授法を知識と技術の両面から習得することが目的です。
したがって上記に示した資格がなければ教えられないということではありません。
教えられる教えられないは資格があるかないかではなく、教えられる知識と技術があるかないかということになります。
生徒が一人いて授業料を払ってくれたならば、そこから日本語教師としての第一歩が始まります。
そして歩き出したなら日本語教師としての勉強は続きます。
英語を媒介語とした教授法なので若干の英語力は必要です。
どのようにして英語を使うかといえば、日本語の意味の英訳と文法事項の説明の時です。
例えば「Watashi wa Kanada-jin desu.」を”I am Canadian."と訳し、それにそれぞれの単語の意味も説明します。
watashi - I
wa - a particle (助詞)
Kanada - Canada
jin - person
desu - am, are, is
ここでは特に助詞「wa=は」の説明が必要ですが、その説明の仕方も授業で教えます。
あくまでも日本語を教えるのが目的ですので、英語は補助的な手段に過ぎません。
英語が上手だからといって1時間の授業で30分も英語を話されたら、生徒はどう思うでしょう。
要は自分の英語力の範囲内で効果的な英語を必要最低限使い、ほとんどの時間を練習に充て、生徒が日本語を自動再生出来るまで何度も言わせます。
本講座の授業自体は主に日本語で進めて行きますが、授業を通して英語力もついてきますので、英語も日本語も習えると前向きに考えられてはいかがでしょうか。
はい、できます。
本校オンライン一般講座の内容は通信総合講座の前半部分の通信一般講座と同じ内容になっております。
通学一般講座修了後に通信マスター講座を受講され修了されますとWJLC日本語教師養成420時間総合講座のCERTIFICATE(講座修了認定証)が授与されます。
なぜ英語を媒介語としたインダイレクトメソッド(間接法)なのか
語学の教授法は直接法と間接法に分けることができます。
直接法とは、例えば、日本語を日本語だけで、英語を英語だけで教える方法です。
間接法とは、例えば、日本語を英語を使って、英語を日本語を使って教える方法です。
私たちが中学校で習う英語は日本語の訳文付きで学習するので、間接法です。
どの言語かを問わず、特に初級の学習者にはその生徒の言語を使って説明しながら教えたほうが、生徒にとってはずいぶんと学習しやすいものです。
ですから英語圏の生徒には英語を使って教えるのが一番効果的だと考えます。
漢字圏の生徒には中国語や韓国語を使って教えるのが理想的ですが、中国語、韓国語ができる日本語教師はあまりいませんので、直接法で教えるしかありません。
ここで直接法と間接法の特徴を比べてみましょう。
【直接法】
-長所-
①生徒の言語に関係なく教えられること。
②日本語を日本語で考える習慣が早く身に付くこと。
-短所-
①ある日本語を教えるために別の日本語で説明しなければならず、その時に目的と手段の混同が生じやすくなり、生徒にその語句の意味が伝わりにくいこと。
②抽象的な語句の説明が困難なこと。
③初級の学習者に対する文法の説明が難しいこと。
【間接法】
-長所-
①直接法では表現しにくい抽象的な語句を生徒の言語で説明出来ること。
②文法事項を生徒の言語で説明できること。
③海外では間接法が主流であること。
-短所-
①生徒の言語によりクラスを分けること。
②教師は媒介語となる言語がある程度出来ること。
いずれにしても状況により使い分けをすれば良いと思います。
日本国内の日本語学校は中国や韓国からの漢字圏の留学生も多いので、ほとんどの学校が直接法を採用しています。
直接法と言ってもまったく媒介語を使わないと言うことではなく、例えば中国人生徒の初級クラスの場合、教室内では日本語だけですが生徒は中国語訳付のテキストを使っています。やはり日本語の意味が分からないことにはどうしようもありません。
それに中国人生徒の初級クラスは日本人である必要はなく日本語が堪能な中国人教師も日本国内の日本語学校で教えています。
日本語教師も日本人だけに限ったものではありません。
海外では媒介語を使った間接法が主流で、市販されているテキストの多さからでもわかるように英語を媒介語とした教授法が多く採用されています。
英語はもはや母国語としている人たちだけのものではなく、世界共通の国際公用語であり、今後もその役割は益々重要になって行くと心得ておいたほうがいいでしょう。
国内でも英語の出来る外国人の方が数多く生活していますので、その方たちには英語を使った間接法の方が無理なく日本語を教えられます。
また、ここでは英語との対比により、学習者の視点で客観的に日本語を捉えて行きます。
例えば「はい」と「いいえ」はいつでも"Yes"と"No"に対応するとは限りません。
そのような違いを知ることで、日本語の特徴を把握していきます。
2017年8月より施行された法務省入国管理局が定めた日本語教育機関の告示基準は以下の通りです。
これはあくまで在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本国内の日本語教育機関(以下、就学ビザが発給できる日本語学校)で働くための条件で、それ以外の国内、国外の日本語教育機関の採用条件ではありません。
以下日本語教育機関告示基準からの引用 http://www.moj.go.jp/content/001265460.pdf
十三 全ての教員が、次のいずれかに該当する者であること。
イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に 関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
ハ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者 ニ 学士の学位(注:4大卒)を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し、これを修了した者
ホ その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
更に本校のような日本語教師養成講座は以下のような条件を満たさなければなりません。
以下日本語教育機関告示基準解釈指針からの引用
http://www.moj.go.jp/content/001264205.pdf
(2)受講した日本語教育に関する研修は、日本語教員養成研修などとして、文化庁に設置された「日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議」が平成12年3月30日に取りまとめた「日本語教育のための教員養成について」において示された「日本語教員養成において必要とされる教育内容」を踏まえ、「社会・文化・地域」,「言語と社会」,「言語と心理」,「言語と教育」,「言語」の五つの区分にわたり、420単位時間以上の研修科目が設定されたものであり、研修の内容について文化庁に届出がなされていること。また、通信による研修(放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる研修に限る。以下同じ。)の場合には、420単位時間以上の研修科目のうち,120単位時間以上は面接による研修又はメディア(同時双方向性が確立している場合に限る。)を利用して行う研修(以下「面接による研修等」という。)であること。
(3)上記研修科目を,教育実習45単位時間以上を含む420単位時間以上修了していること。また、通信による研修の場合には、420単位時間以上の研修科目のうち、120単位時間以上は面接による研修等により修了していること。
また、日本語教育機関告示基準ニの日本語教員養成研修が適正かどうかを審査するのは文化庁で、その審査に合格しなければ日本語教員養成研修(注:いわゆる日本語教師養成講座)としては認められません。
詳細は文化庁の420時間日本語教員養成研修を参照のこと
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoin_kenshu/index.html
日本語教育機関告示基準(以下、新基準)に関しては本校のQ&Aでも述べていますが、http://wjlc.com.au/questions#A02
ここは本講座と新基準について、以下Q&Aの形でできるだけわかりやすく説明いたします。
Q1:私は短大卒ですが、文化庁に認められた機関の420時間日本語教員養成研修を修了すれば、だれでも在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本国内の日本語教育機関(以下、就学ビザが発給できる日本語学校)で働けますか。
A1:いいえ、新基準ではその前提として4大卒か大学院卒でなければなりません。つまり、学歴が4大卒中退、短大卒、専門学校卒、高卒、中卒の場合は、文化庁に認められた機関の420時間日本語教員養成研修を修了しても就学ビザが発給できる日本語学校では働けません。
Q2:ワールドジャパニーズランゲージセンター(本校のこと、以下、WJLC)は新基準の審査の対象校になりますか。
A2:なりません。新基準の審査の対象校は通信、通学にかかわらず、日本国内の日本語教師養成機関に限られています。本校はオーストラリアにあり、また、本講座は文化庁に認められた機関の420時間日本語教員養成研修と違い、学歴、年齢、国籍も不問で、しかも120時間以上の面接が受けられないような方のための講座です。メディアを使っても120時間以上の面接が必要となるといろいろと時間や場所の束縛や制約が出てくることになり本校のモットーである、「自由な時間、自由な場所」での学習ができなくなります。本校の卒業生の中には病院のベッドで修了なさった方や現在もベッドの上で受講なさっている方もいらっしゃいますが、そのような方は直接あるいはメディアを使った120時間以上の面接は物理的にも時間的にも無理があります。実際に仕事をしながら120時間以上の面接を課した講座を受けるのは大変なことで、現在の仕事に支障をきたすことにもなりかねません。
本講座はもともと受講者の現在の生活環境をリセットさせることがないように配慮したものであり、通信教育のメリットを最大限に活かし、どういう生活環境・地理的環境の方でも受講して日本語教授法を習得させることが本講座の社会的使命と考えています。30年以上、海外、離島、障碍者あるいは仕事や家庭から離れられない人などのために講座を開講してきましたし、今後もその講座開講の目的は変わりません。また、新基準はその対象者が日本国内で働くことを前提としており、ほとんどの在日、海外の外国人は実質的に対象外となりますが、本講座では日本語能力さえ満たせれば、前述の通り、日本語教師になるという夢の実現に、どなたでも受講できるように受講資格に国籍や年齢を問うておりません。したがって、基準が変わり、国外の日本語教員養成研修が認められるようなことになっても、通信以外の講座受講が困難な方に120時間以上の面接を行う講座を開講する予定はありません。
Q3:4大卒でなくても本講座を受講し、かつ日本国内の就学ビザが発給できる日本語学校で働くにはどうすればよいのでしょうか。
A3:毎年10月に日本国内の大都市で行われる日本語教育能力検定試験に合格すれば、格安(14,500円)かつ学歴に関係なく応募基準を満たせます。
Q4:本講座は日本語教育能力検定試験のための対策講座としても役に立ちますか。
A4:はい、本校の在校生、卒業生より検定試験合格の知らせが届いていますので、一部を紹介します。
https://www.wjlc.com.au/notification07042018-1100
副教材として前年度の検定試験問題を含めていますが、講座の中で試験問題についての詳しい解説も行っていますのでこれらを使って検定試験に備えることができます。
Q5:本講座の最大の特徴は何ですか。
A5:日本語を教える際に英語を媒介語にした間接法による教授法と、日本語を日本語で教える直接法による教授法の二つの教授法が習得できるということです。
特に、英語を媒介語にした日本語教授法の講座は本校以外の教育機関ではほとんどありません。しかし、英語圏や英語の理解がある人々の国においては英語を媒介語にした間接法による教授法が主流です。加えてこの教授法を習得すれば、他言語を英語に替えて教えることも可能です。
Q6:受講生は本講座をオーストラリアや日本以外からも受講していますか。
A6:はい、受講生は世界70ヶ国以上から本校の通信講座を受講していますが、これは英語を使った教え方が世界では一番通用しているということだと思います。
Q7:今後日本語学習者は増えるのでしょうか。
A7:はい、現在世界で約400万人の日本語学習者がいると言われ、そのほとんどが日本国内ではない海外の学習者ですが、2020年の東京オリンピックの開催に伴い、今後は更に海外での日本語学習者が増えるのではないでしょうか。本講座で習得した日本語教授法の活躍の場ももっともっと広がりをみせることとなるでしょう。
Q8:私は身体的に外出が難しく本講座受講後、自宅でスカイプで日本語を教えたいと考えているのですが、それは可能なのでしょうか。
A8:はい、可能です。本講座卒業後、スカイプなどを使いオンラインで日本語を教えている卒業生は年々増えています。しかも英語を使って日本語を習いたい学習者は英語圏に限らず世界中にいます。
以下、最近本420時間日本語教師養成通信講座を卒業したロス在住の日本人男性の感想です。
「現在マンツーマンで欧米の生徒中心にオンラインでレッスンをしています。
日本語を学びたい生徒が思っていたよりはるかに多く驚いています。これからオリンピックも開催されるので更に増えていくのではないかと期待しています。」
Q:日本語教師の資格とは何ですか。
A:日本語教師においては国家免許という公的な資格制度はありません。従って医師や弁護士のような国家試験、あるいは学校教員や幼稚園教諭のような地方教育委員会による採用試験などもありません。
Q:日本国内の通学の420時間日本語教師養成講座のほとんどが60万円前後の受講料です。WJLCの通信の420時間講座との違いは何ですか。
A:まず、日本にある日本語教師養成機関の通学講座の受講は60万円という大金を払わなければなりません。違いといえば、2017年8月1日より実施される法務省の日本語教育機関の告示基準によると日本国内の在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関(以下、就学ビザが発給できる日本語学校)で働く場合に420時間の通学講座か通信でも120時間以上の面接(我々はこれは通学講座と実質的に同じだと考えています)がないと働けないとしており、WJLC講座(以下本講座)の全過程通信講座の場合はその条件を満たしません。しかしながら、その大前提として4年生大学卒か大学院卒でなければなりません。つまり、最終学歴が大学中退、短大卒、専門学校卒、高卒、中卒の場合、420時間の通学講座を修了しても就学ビザが発給できる日本語学校では働けません。
また、4年生大学卒か大学院卒で420時間通学講座を修了しても他の職業と同様に単なる必要条件に過ぎず、就職の保証はどこにもありません。就学ビザが発給できる日本語学校で働く条件に「日本語教育能力検定試験」合格があります。これは実習を伴う研修等は必要ありませんか ら本講座を受講しながら検定試験に備える勉強をすることも可能です。実際に本校の受講者や受講修了者で検定に合格した人は少なくありません。どうしても日本国内の就学ビザが発給できる日本語学校で働きたい方は検定試験合格を目指したほうがよろしいのではないでしょうか。本校のオンライン一般口座とWJLC通信マスター講座を受講しながら検定試験に合格すれば、時間的にも経済的にもずっと節約できます。前述の通り、60万円といえば大金ですが、そんな大金と多くの時間を費やす前にここは慎重にお考えになったほうがいいのではないでしょうか。以上は日本国内の就学ビザが発給できる日本語学校での話で、他のQ&Aでも触れていますが、日本語はそれ以外のところでも教えられています。
Q:日本国内の在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関以外の日本語教育機関とは具体的にはどんな学習者でしょうか。
A:永住ビザ保持者、ビジネスビザ保持者、ワーキングホリデービザ保持者、観光ビザ保持者、大学などの他の教育機関の就学ビザ保持者及びその家族等が該当します。したがって、就学ビザの発給を必要としない学習者を教える日本語教育機関において、日本語教師として教える場合は個々の日本語教育機関の内規により採用条件は異なります。 申し上げるまでもなく、個人レッスンや企業への出張レッスン、ボランティアレッスンは、日本語教育機関に属さなくても日本語を教える能力の証明があれば可能です。法務局の日本語教育機関の告示基準解釈指針は日本国内に限定適用されるもので、日本国以外の国では適用外となります。 無論、日本国以外の国においても、それぞれの日本語教育機関運営既定や採用基準はありますが、本校講座修了者が多くの国で日本語教師として採用されていますことから海外では通学教育と通信教育を分けて教師採用条件にしているところはほとんどないのではないかと推察します。
Q:2017年8月1日より実施される法務省の日本語教育機関の告示基準によると日本国内の在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関(以下、就学ビザが発給できる日本語学校)で働く場合に通信の420時間の日本語教師養成講座は120時間以上の面接が必要とありますが、こちらではメディアを使って120時間以上の面接は受けることは可能でしょうか。
A:いいえ、できません。というより、本講座は120時間以上の面接が受けられないような方のための講座です。メディアを使っても120時間以上の面接が必要となるといろいろと時間や場所の束縛や制約が出てくることになり本校のモットーである、「自由な時間、自由な場所」での学習ができなくなります。本校の卒業生の中には病院のベッドで修了なさった方や現在もベッドの上で受講なさっている方もいらっしゃいますが、そのような方は直接あるいはメディアを使った120時間以上の面接は物理的にも時間的にも無理があります。実際に仕事をしながら120時間以上の面接を課した講座を受けるのは大変なことで、現在の仕事を失うことにもなりかねません。本講座はもともと受講者の現在の生活環境をリセットさせることがないように配慮したものであり、どういう生活環境・地理的環境の方でも受講して日本語教授法を習得させることが本講座の社会的使命と考えています。30年以上、海外、離島、障碍者あるいは仕事や家庭から離れられない人などのために講座を開講してきましたし、今後もその講座開講の目的は変わりません。したがって、通信以外の講座受講が困難な方に120時間以上の面接を行う講座を開講する予定はありません。
Q:日本国内の就学ビザが発給できる日本語学校で働く場合の条件を満たす一番安上がりの方法を教えてください。
A:1年一度日本国内の大都市で行われる「日本語教育能力検定試験」に合格することです。受験料は10,600円でこれに合格すれば、学歴が中卒、高卒の方でも日本語学校で働く場合の条件を満たすことができます。わざわざ貴重なお金60万円と日本教師養成講座通学のための420時間を費やす必要がなくなります。また、この試験は独学で参考書や過去問で試験対策をすることにより合格することも可能です。ただし、一般の日本語教育に携わったことがない方は本校の420時間通信講座で日本語教育とはどのようなものかを学習して試験にチャレンジなさったほうがはるかに合格に近づくでしょう。なぜかといえば、日本語文法はまったく日本語教育の学習をしたことがない人にとっては、理解するだけでも本当に大変だからです。検定対策書を見ただけですぐにギブアップするぐらい専門的なものです。それゆえ、本講座で基礎知識を学んでおく必要があります。その基礎知識があれば試験内容の理解は難しいものではありません。
Q:「日本語教育能力検定試験」に合格しただけで、実際に日本語が教えられますか。
A:検定合格者は採用の際に有利になり、またそのための勉強もいい意味で本講座の学習の励みとなりますから、本校としても検定合格を奨励していますが、検定試験はあくまで学科試験のみで、合格者はいわゆるペーパードライバーです。仮に日本語教師として採用されても日本語教授法を身に付けていなければ教えることは難しいのが現実です。本講座の修了生の中には受講前に検定試験に合格し、その後本講座を受講なさる方もいますが、検定合格だけでは実際に教えることは無理だと異口同音に言っています。以下はそのような方の本講座修了後の感想です。
「毎回、詳しくわかりやすく細かいご指導をありがとうございました。受講前に日本語教育能力検定試験には合格していました。しかしながら、合格しているだけでは、授業の組み立て、学習者への文法、用法の指導など、順序立てて行う方法がなかなかうまくいかず悩むばかりでしたが、この講座で具体的な説明法や例文等を学ぶ事が出来大変参考になりました。現在駐在外国人に個人授業をしておりますので、間接法による指導が中心です。特に英語での説明法、文法用語などはとても役立っております。」
Q:海外青年協力隊等に応募する場合に420時間養成講座の通信と通学では採用される場合に違いが生じるのでしょうか。
A:国際交流基金、あるいはJICA(国際協力機構)が海外青年協力隊等における日本語教師を募集する際、420時間程度の日本語教師養成講座修了者であれば、学習手段は通信でも通学でもどちらでも応募条件を満たすとしています。ただし、それ以外に実際に教えた経験があればなお良いとのことです。
Q:420時間養成講座の通信では実習が含まれませんが、どうやってカバーするのでしょうか。
A:本校講座では実習を含めない代わりに、教育実習をしている受講者を撮影したDVDを教材に含めています。教育実習は良い教師になるための手段であって目的ではありませんから、それに代わる学習方法があればそれで補えるところは多々あると考えます。
Q:通信講座の場合、ワークシートの提出方法を教えてください。
A:インターネット(Eメール)での提出を原則としますが、パソコンをお持ちでない方はFAX、郵送でも提出することができます。
Q:どのくらいでマスター講座を通信講座で修了できますか。
A:1日1時間30分の学習で約8ヵ月間、1日3時間の学習で約4ヵ月間で修了できます。
Q:マスター講座の有効期限を教えてください。
A:マスター講座は2年間あります。
Q:420時間総合講座は特に低料金なのはどうしてですか。
A:受講料については、日本語教師養成一般講座と420時間通信講座(通信マスター講座)を合せて日本円で175,000円(2020年1月 現在)です。この金額は日本にある民間の日本語教師養成420時間講座の受講料と比較した場合、3分の1程度の料金です。これはお調べになればすぐ に判明しますが、ほとんどが60万円前後になります。もちろん受講料金が安ければ良いというものではありませんが、WJLCでは無駄なコストを抑えて講座内容を効率化したため、低料金で充実した講座を開設することができました。「まずは生徒の身になって考える」がWJLCのモットーですから、低料金設定は受講生の利益に繋がると確信しています。
Q:WJLC420時間講座のメリットは何ですか。
A:WJLCの日本語教師養成420時間講座は通信教育ですから世界中どこからでも受講ができます。また、それだけではなく日本語教師の資質の向上にも十分な配慮をしています。第一は日本語教授法の習得です。受講者は英語を媒介語とした間接法と日本語を日本語だけで教える直接法という2つの異なる教授法を習得することができます。これによりほとんどの日本語学校の求めに応じることが可能です。特に英語を媒介語にした教授法習得者は極端に数が少なく英語話者が多い学校などでは採用される確率が高くなります。第二に日本語教育能力検定試験にもある程度対応できるようなカリキュラムで学習しますから検定試験合格も確率が高くなります。
Q:日本語教師養成420時間講座は通信講座受講でも可能ですか。
A:可能です。本講座は30年以上の実績があり、多くの受講者が世界中に日本語教師として活躍しています。本講座では長年の研究と実績で培った日本語教育メソッドを通信講座に反映させて、誰でも合理的に日本語教授法を習得できるシステムを開発しています。それとともに、講座受講希望者においては地理的、時間的あるいは経済的、身体的に通学の受講が不可能な人も当然想定されるわけで、そのようなハンディのある人たちの便宜を図る意図でも開設されているのが本校通信講座です。通信講座での日本語教授法習得が可能ということについては、多くの受講者が世界中で活躍している事実が証明しています。
Q:WJLCの講座と他校の講座との違いは何ですか。
A:講座前半の内容は英語を媒介語にしたインダイレクトによる教授法を中心に学習しますから、この教授法の講座は他校ではあまり見られないと思います。講座後半では他校の講座内容が文化庁の新シラバスに準拠した内容であればWJLCの講座と似たような内容になるでしょう。
Q:WJLCの修了証はオーストラリアの教員免許に、例えば日本教師の免許として資格が付与されるのですか。またTafe CollegeやPrivateの語学学校で教えることはできますか。
A:日本語教師の免許については、例えばこちらの公立高校などで語学教師として就職する際の教員免許を想定されているのであれば、その際は州の教員免許が必要になり、本校の修了証では条件を満たしません。大学で教鞭をとる場合は言語学などのマスタ-を取得していれば特別に教員免許は必要ないところが多いようです。Tafe CollegeやPrivateの語学学校で教える場合も基本的に教員免許は必要ないと思いますが、大学を含め学校により採用基準が異なるので直接お問い合せになるのが確かでしょう。
Q:講座終了後どのようなところで働くことができますか。また講座を終了した人はどのような方法で仕事を見つけていますか。
A:基本的には日本語を教える私的な学校やプライベ-トレッスンが主になると思います。もちろん住んでいる国の教員免許があれば公立の学校でも教えられますし、大学でもマスタ-を取得していれば大学で教えるチャンスもあります。本校の講座修了者の中には現役の日本語教師も少なくありませんし、新たに日本語教師になった人ももちろんいます。就職の採用条件というのは、国によって異なりますし、日本語教育機関によっても異なりますから、一概にこれだけの条件が揃えば就職できるということは言えません。
Q:どのようにしてオーストラリアで仕事を探したらよいでしょうか。
A:仕事を探す方法として、一つは仕事を紹介・斡旋する専門の会社に依頼する方法と、もう一つは自分で探す方法があるかと思います。前者の方法は直接会社にお問い合わせになって求人状況採用条件などを確認し登録しておきます。後者の自分で探す方法は、本サイトの仕事の探し方の欄に載せております。
Q:講座終了後、就職の斡旋や紹介を標榜する日本語教師養成学校がありますが、WJLCには就職の斡旋や紹介のサービスはありますか。
A:WJLC では、就職の斡旋や紹介を本校講座の受講条件のギャランティーにはしていません。それはしたくてもできないというのが正直な答えです。就職に際しては日本語教授スキルだけではなく、多くの条件が付帯します。海外であれば、VISAのカテゴリー、年齢、その国の教員資格、英語などの語学力、経験、PCや運転免許などの特殊技能などに加え、人格面なども考慮されます。それから採用の時期やタイミングなどもあります。もしも、上記の条件を一つも満たさない人に、就職の確約をすることは常識的に無理だと言わざるを得ません。本校でも講座受講生や修了生に個人的に仕事の紹介をすることはありますが、あくまでも採用条件を考慮して誰が適任であるかこちらで判断した場合です。さもなければ、雇う側、また日本語学習者、それに本人にも迷惑な結果になることが懸念されるからです。
Q:海外で日本語を教えるにはどんな資格が必要でどのような準備をしたらよいでしょうか。
A:まず、正しく効果的に日本語が教えられる技術を身につけておくということが大前提ですが、人格的な問題があれば、教師として採用されることは常識的にありません。教師の質が学校の質を決める大きな要素ですから、これも経営者の側から考えれば至極当然なことだと思います。また、資格としてはビザの問題や語学力、学歴、職歴等その国やその国の教育機関により様々ですから、事前にお調べになったほうがよろしいかと思います。
Q:日本語を教えてほしいと頼まれましたが、プライベ-トの授業料の相場はいくらぐらいでしょうか。
A:特に定まったものはありませんし、国よって相場が異なるかと思います。オーストラリアでは、教師の家で教える場合は、ふつう1時間A$20~40位でしょうか。だいたいこの料金を基準にして以下のことを考慮して算定してください。
生徒の人数により、例えば1人だけであればA$30、2人一緒ならA$50(一人当たりA$25)、3人一緒ならA$60(1人当たりA$20)のように算定します。生徒の年齢や専門性も考慮します。幼児の場合は遊びの要素が多くなるし、一回のレッスンで習得させる内容も少ないので、あまり高い授業料は徴収できません。逆に、授業の準備が大変なもの、例えば、HSC受験・大学の専門教科(古典/漢文/エッセイなど)は料金の設定を高めにしてもいいでしょう。授業料の一括払い(例えば、10回分先払い)や長期契約(1年)などの場合は、少し安くすることも考慮してあげてください。一般的に申しますと、日本語教育のプロとして教えるわけですから、あまり安い授業料は感心しません。授業の質に見合った金額を請求してよいと思います。ただし、経験を積むことを重視して多くの生徒を教えるのが目的なら、時間のA$15でも十分だと思います。以上のことを参考にして授業料を決めてください。
Q:WJLCのテキストを使って日本語を教えているのですが、生徒はテキストを読むだけで理解し、私が説明することがほとんどないのですがこれでよいのでしょうか。もしもこのテキストがなければどのように教えたらよいか少し不安です。テキストを使わないで教えることも可能なのでしょうか。また実際の授業では英語力のある先生の方が有利だと思うのですが、それについても意見を聞きたいです。
A:語学教育の目的は生徒の言語習得の実現というものですから、テキストはあくまでもその目的の補助的な役割をするもの、つまり学習手段の一つです。それゆえテキストを使う使わないは教授法により異なって然るべきですが、生徒が体系的に語学の学習を行う際には非常に有効な教材です。本講座は日本語教師の養成ですから、どのように生徒に日本語を教えるかを学習します。従って体系的にまとめられたテキストは欠かせません。例えば、どう導入して、どう説明して、どう練習させるか、その教授過程(生徒の習得過程)をテキストを通して本講座受講者の皆さんに学習してもらいます。
ご質問者のおっしゃるように、このテキストを使って順番通りに教えて行けば、それほど教えるのに苦労することはありませんが、それは教師が内容をよく把握しているという条件が付随します。全く日本語教授法の勉強をしたことがない人にこのテキストを渡して日本語の授業をさせても、できるものではありません。このテキストがやさしくまた合理的だと思うのは、すなわちテキストの内容がよく理解できている証拠にほかなりません。それから、学習者がこのテキストを読むだけで日本語を習得できるかというとそれも無理です。やはり教師が肝心なところを教えなければ習得は難しいと断言できます。
それから教師の英語力についてですが、なるほどご質問者がおっしゃるように、英語話者に教授する際は教師に英語力があるに越したことはありません。しかし日本語教師は英語の先生ではなく日本語の先生です。英語は手段です。だから下手な英語も上手に使えば目的は達せられ ます。もし、英語の説明を完璧に言えるようになりたいということであればわざわざ英会話学校に行く必要はありません。テキストの説明文を一日百回真剣に声に出して読めば、誰でも諳じることができるようになります。そしてテキストを使って何度も教えながら自分の言葉で説明できるように実践の場で英語力を磨くほうが効果的だと考えます。
教師の英語力についてはしばしば質問を受けますが、もし英語をネイティブスピーカーの教師に習うとき、教師に完璧な日本語を期待あるいは要求するかどうかを考えてみてください。英語の授業なのに立て板に水の如く日本語を話されたら食傷気味になるのではないでしょうか。日本語の授業もそれと同じで生徒は教師の英語を聞きに来ているわけではありません。英語は日本語を理解させるための補助的な手段であり目的ではありません。その意味では必要最低限の英語力で十分です。要は英語を使って教師がどう効果的に教えられるかということです。
Q:できない生徒のプライドを傷つけずに指導する方法があるのでしょうか。一人の生徒はドリルなどもあまり真面目にしませんし、やらせてもできず、その割にはプライドが高くてできないことを素直に認めません。このような生徒をどう指導してよいか分からず、最近教師の限界を感じています。私自身、生徒に完璧をもとめるところがありよくないと反省していますが、どのへんまで妥協すればよいのか教えてください。
A:教師の仕事は人間を相手にするものですから機械的に教えればよいというわけには行きませんし、生徒の性格や学習能力、生活・学習環境なども十分把握しておくことは教授する上で必要だと思います。また、教師と生徒との間にお互いの敬意や信頼がなければ学習の継続は困難だろうと考えます。それを踏まえた上で教師は生徒の学習目的に応じてリ-ダ-シップを発揮して授業を行わねばなりません。
今回、お尋ねのケ-スの「生徒のプライドを傷つけずに指導する」ということについては、個々の状況によって対処の仕方が異なりますから、画一的な指導はできないと思います。ただ一般的に言うと生徒の学習評価をする場合、学習能力より学習態度を重視した授業が望ましいかと思います。学習態度が正しければ、学習能力は必ず開発されていきますから、まずそのことを本人を含めクラス全体に周知させることです。間違いも、そこで矯正されれば、間違いではなくなります。目標言語習得ということについては、学習者の語学センスや才能により差が出るのは確かですが、何人といえども完全な人はいませんし、できる人は例外なく非常な努力が実を結んだ結果です。そういう過程を経てはじめてものにできるのが語学ですから、教師も生徒も常に完璧を望めばそこに無理が生じます。練習はできないから、できるようにするのが練習であり、最初からできれば練習は必要ないわけで、その辺りの認識を持たせたらいかがでしょう。もし練習の文が長ければ大事なところだけに端折っても構いませんし、必ずしもテキスト通りにやる必要はありません。それこそ、生徒の能力に応じて臨機応変に対応してください。
学習内容が進めば段階的に難しくなりますから、生徒ができないところはやはり曖昧にせず、きちんと教えてください。そういう意味での厳しさは必要です。ただ、クラスの中でその生徒が浮き上がるような状況は好ましくありません。他の生徒に対してもけしてよい影響を与えません。そういう場合にこそ教師の力量が問われます。生徒ができないからといって、その生徒を否定することはできません。別の分野ではすばらしい才能を発揮する人も当然います。ですから、日本語の中でも得意な部分(読み書き、単語力、コミュニケーションスキル等)を見つけてやり、その方面から自信をつけさせる方法なども考えられます。教師には、包容力、忍耐力、統率力と共に生徒の才能を引き出すという力も要求されます。
パナリンガ学院の故長島達也先生が「教師は産婆だ」というソクラテスの喩えを常々おっしゃっていましたが、教師には生徒の才能を引き出す役目があると理解しています。少し話が外れましたが、大事なことは生徒がわからなくてもそれでプライドが傷つくようなクラスの空気を作らないこと。また一人の生徒が上達すればそれがクラスの喜びになるような空気を醸成することが教師の役目だと思います。どのへんまで妥協すればよいかということですが、評価は教師の基準ではなく個々の生徒のレベルに応じて行うものです。ご自分が完璧主義だからそれを生徒に求めるのは間違いです。逆の立場になれば想像できるかと思います。評価を100から減点していくのではなく、0から加点していくようにすれば、誰しも最初の0より進歩・上達した評価になります。それだと妥協などという言葉も不必要になるかもしれません。十分です。要は英語を使って教師がどう効果的に教えられるかということです。
Q:ワ-クシ-トの課題意図は何ですか。テキストがよくできているので課題は英語で答える問題が多いほうがよいのではないでしょうか。
A:英語で答える問題が多いほうがよいのではとのご意見ありがとうございました。今後講座の内容をより充実させていく上で参考意見として検討事項にいたします。現在のワ-クシ-トの課題学習の意図を申しておきますと、まず教師自身が英語との比較の上で日本語文法を理解すること。また段階的、体系的に教えていくには、どこにポイントをおいて教えるのかそのコツを掴むこと。そのためには英語話者の思考傾向を知ること、そして前述したようにいろいろな角度から考えを導きだせるように訓練することなどを、課題の学習で習得してもらうことです。もちろん英語での文法説明ができなければ英語圏で日本語教師はつとまりません。そこで英語でどう説明すればよいか、それはテキストに載せているとおりです。口頭で説明する際もテキストの文法説明文をそのまま読んでやれば生徒が理解できるように考えられています。だから基本的にはテキストの文法説明文を暗記すればテキスト無しでも教えられますし、それは受講生の学習意識の問題になります。ただし、日本語教授の理解がなければテキストの内容を生徒に教えることはできません。本校のテキストが合理的に編集されていると分かるのは、日本語教授法の理解があるためです。また皆さんにその理解がなければ、日本語学習者にテキストだけ読ませても日本語習得は難しいと思います。
Q:教師は授業でどの程度日本語を使って教えるべきか、またある程度学習者が日本語を理解するようになった場合でも英語を使うべきか教えてください。
A:語学教授法において、媒介語を使う大きなメリットに「目的と手段の混同が避けられる」ことがあります。つまりこれを逆に考えると、教師が媒介語を使わず日本語だけで授業を行った場合、生徒は学習する日本語と説明のための日本語との区別が曖昧になります。教師は学習者が学習する内容を明瞭にしてあげなければなりませんから、混乱させるような日本語の使い方は避けるべきだと考えます。ただし学習者も日々日本語を習っていくわけですから、教えた日本語は教師も使うべきだし、生徒にも使わせるようにします。
それから、初級者でも教室用語などはいつも使うものですから最初から日本語(意味の説明はすること)で言ってよいでしょう。学習者のレベルが上がればそれに応じてより日本語を多く使うことはいうまでもありません。もっとも文法的説明などは説明が主ですから、わざわざ日本語にこだわる必要はないと考えます。基本的には、説明は英語で練習は日本語でというのがベタ-だと思います。最も教師として大事なことは、生徒が日本語を習得するために「何が望ましいのか」ということを常に念頭において授業に臨むことではないでしょうか。また、それは自分が生徒の立場になって考えることを意味します。もしも、英語の授業でネイティブの教師が必要以上に日本語を使えばどう感じるでしょう。また、理解不可能なレベルの英語でまくしたてられたらどう思うでしょうか。おそらく両方とも授業への興味が半減するでしょう。言語を教える場合に注意しなければならないのはこのような授業です。生徒にとって何が望ましいのかという意識が希薄になると教師の一人相撲の授業に陥ります。媒介語を使う場合も上記のことを銘記して、授業プランをしっかり練って授業に臨んでください。
Q:生徒が日本語を学ぶにあたって何が難しいのでしょうか。また媒介語を使うと母語の干渉が上達を阻むと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
A:最初のご質問は非常に抽象的なのでお答えにくいのですが、あなたは何がやさしく、何が難しいとお考えですか。このような問題を考えるとき、もう少し具体的に問題を整理して質問するといいですね。言語を習得する過程において、二つの面を克服しなければなりません。一つは言語要素の規範であり、もう一つは言語運用です。言語要素の規範とは、音声・音韻・アクセント・語彙・文法・文字・表記法などのル-ルであり、言語運用とはその規範に従って話し、聞き、理解すること、すなわち運用の仕方・言語運用能力のことで、この両面ができなければ、学習言語で自己表現をすることは難しいわけです。
個々に何が難しいといっても、それぞれ学習目的(到達目標)、教授法、学習環境、年令などにより異なってきます。ただ一つ言えることは、成人の学習者の場合、母語からの影響や抵抗が強く、これが二つ目のご質問「母語の干渉」といいますが、確かにこの問題が日本語習得に関して一番大きいと思います。言語はコミュニケーションの手段でありながら、一方でその言語を用いる国の人の思考方法、認識方法、生活・行動様式、自然環境、社会習慣、文化形態などと深くかかわっています。だから、ある言語から別の言語に翻訳された同じ意味・概念を指すとされる言葉でも、厳密の一致はほとんどありません。抽象的な言葉は言うに及ばず、日常使用頻度が多い形容詞などでも同様です。
日本語と英語で例を挙げると、‘暖かい’は‘warm’、‘涼しい’は‘cool’ですが、これは英語では一年中使われます。しかし、日本語では夏あるいは秋にかけて用いられるのは‘涼しい’であり、けっして夏に‘暖かい’とは言いません。また冬あるいは春にかけては‘暖かい’であり、けして冬に‘涼しい’とは言いません。日本語で‘暖かい’は寒い中で暖かい結構な日和であり、‘涼しいは’暑い中で涼しいという結構な日和であるという気分も含まれます。だから一般的に良い意味で使われます。英語の場合は、ただ単に体感気温(温度)を‘warm’‘cool’と表現するわけでそこには話者の結構であるという気分は表現されません。こういう問題を対照言語学が扱うわけですが、日本語教師も当然認識しておかねばなりません。母語の干渉は媒介語を用いるために起こるという説があり、ご質問者もそれを指してのことだと思いますが、直接法であれ間接法であれ、教師及び生徒にその意識が希薄であれば母語の干渉は避けられません。英語圏の人に、いくら直接法で‘暖かい’を教えても、学習者は‘warm’だと認識するだけです。
翻って言うと、そのような誤解は直接法での学習者の方が多くなる可能性があります。たとえば英語教師が直接法で‘short’という単語を示し、身振り手振り、あるいは長さの長短のあるものを用いてその意味を伝えようとしたとします。その時、日本人であれば「これは‘短い’という意味か」と合点するでしょう。しかし、その合点は日本語で理解した合点であり、つまり翻訳です。ただその合点が正しいのかどうかの確認が言葉でできないだけです。このように母語からの干渉は教授法の別に関係無く起こるものです。その点、媒介語を使う教授法ではその意味の差異を説明できることにより母語からの干渉を軽減させることができます。
Q:可能形の「ら抜き言葉」が定着しているようですがそれで教えてもよいでしょうか。
A:現在‘ら抜き言葉’が使われている状況を説明する必要はありますが、‘ら抜き言葉’で可能形を教えることについては反対です。その理由として以下の4つの点が挙げられます。
(1) 文法的に合理的説明ができないこと。
(2) 「ら抜き」にならないものも少なくないこと。
例)「信じられる」「生きられる」など。
(3) 辞書形が同形で第一群に属す動詞と区別ができないこと。
(例)「帰る(帰れる)」と「変える(変えられる)」など。
(4) 「ら抜き」は音声学的に母音の /a/が欠落することにより、音が汚くなること。
私は外国人に可能形を教える際には、必ず生徒に‘ら抜きの可能形’と比較させてどちらが響きがよいか尋ねます。すると100%間違いなく‘ら抜きの可能形’ は音がよくなく、「ら」が入ると音が美しいと言います。私は文法云々よりもこの事実だけでも‘ら抜きの可能形’を使いたいとは思いません。無論生徒も使いたいとは言いません。‘ら抜き言葉’に関しては許容ということで公のお墨付きをもらい有名な作家をはじめテレビ・ラジオその他日本中の人が使っている現状は承知しています。生徒にもその現状は教える必要はありますが、日本語教師が率先して使うのははっきり言って不見識だと考えます。この私の見解にはいろいろと批判があるかもしれませんが、日本語教師には正当で美しい国語を継承しようとする気概も必要だと思います。
Q:ら抜き言葉の話は興味深く読みましたが、「あるじゃないですか」など最近の言葉遣いに対する日本語教師の態度はどうあるべきでしょうか。私は何か軽佻な感じがして使いたくないのですが。
A:私も前々から「~じゃないですか」という表現が耳障りで仕方がありませんでした。特に「あるじゃないですか」に至っては非文ではないかと思います。「ないじゃない」という言い方はありますが、「あるじゃないですか」はほとんど見たことも聞いたこともありませんから最近の流行言葉でしょう。「新種語も会話の中で日常的に馴染んでくれば慣用語として許容される」と言いますが、ただ単に表現力のなさを誤魔化すような言い方は言語文化の低下を招くだけです。積極的には使わないのが賢明だと考えます。もう一つこの頃の流行に「買うよみたいな」という言い方がありますが、これなども同類ではないかと考えますが、今では、民放は言うに及ばずNHKのレポ-タ-なども使っていますから、日本中また世界の日本人の中に蔓延しても仕方がないかもしれません。
それでは日本語教師は言語に対しどのような態度をとるべきか、私見を申しますと、違和感がある言葉は断じて使わない。それが言語に携わるものの見識だと思います。ついでに申しますと、物事の好悪を言うのは慎むべきことですが、こと言葉に関しては自分の言語感覚を麻痺させないためにも使う上での好き嫌いはあって然るべきだと思います。ただし、それはあくまでも自分の問題で人に強要するものではありません。なぜかと言うと、言葉それ自体に善し悪しがあるわけではなく、善し悪しは言葉を使う側の意識の問題だからです。その意味では差別語なども同じだと言えます。抽象的な思考からは抽象的な言葉しか生まれませんし、本人に品位がなければ言葉も下品になります。日本語教師は、そういうことを十分認識しておく必要があると考えます。それから、現代日本語として許容されている表現を生徒にどう教えるかという問題がありますが、これは正当な表現を教えた後に紹介する程度でよいかと思います。
Q:「私は彼を好きです」は文法的に許容された文だと何かの本で読んだ記憶があるのですが、「私は彼を好きではありません」という否定の表現にも助詞「を」は使われるのでしょうか。
A:「私は彼を好きではありません」という否定の表現には、「彼が/彼は」とするのが普通で「彼を」はあまり聞かないと思います。二年前に本校が教師養成講座受講者に行った調査では「酒を好きじゃないが飲んだ」「酒を嫌いだが飲んだ」という表現は違和感があるかという質問にほぼ全員が「ある」と答えています。これはあくまでも語感の問題であり、否定形が文法的に許容されないとはどの文法書にも出ていません。しかし、「~は~を好きじゃない」という文型も出ていません。ほとんどの文法書では対象語には「が」を取るとして、「を」については触れてもいません。すなわち、否定形は認知されていないというのが現状ではないでしょ うか。少なくとも否定形の「を」の認知にはまだ時間がかかるのではないかと思います。なぜ肯定形の場合「を」が許容されるようになったか、それは、「が/は」だけでは主語と対象語の判別が付けにくい場合があるという理由からです。そのような場合に「を」で対象語を表せば、主語と対象語が明瞭になります。だから特に口語で使われるようになったと聞いたことがあります。ただし、口語でも否定形は主語にしろ、対象語にしろ「は」が取られることが多く、「を」で対象語を示すことは少ないと考えます。もし使われるとすれば、肯定のときと同様に文脈あるいは状況から主語と対象語の判別が「は」では明瞭ではない場合に限られるでしょう。